![]()
北播磨編
| 丹波市編Ⅰ | 丹波市編Ⅱ | 篠山市編Ⅰ | 篠山市編Ⅱ | 篠山市編Ⅲ | 篠山市編Ⅳ | 北播磨編 | 東播磨編 |
| 東山古墳群多可郡 | 村東山古墳多可郡 | 岡福谷池古墳 西脇市 | 滝ノ上古墳・岡ノ山古墳 西脇市 | 経ヶ芝古墳 西脇市 |
| 道ノ上古墳 西脇市 | 西岡古墳群 西脇市 | 寺内古墳群 西脇市 | きつね塚古墳 西脇市 | 下山古墳 西脇市 |
| 小苗古墳群 西脇市 | 八日山古墳1号 西脇市 | 上本町大塚古墳1号 西脇市 |
![]()
東山古墳群 多可郡那珂町中
妙見富士カントリーと多可高等学校の西隣一帯(妙見山登山口)に丸い芝生の小山の起伏が点在する
「東(ひむかし)山古墳群」がある。
此処には調査を終え「北はりま田園空間博物館」として公園整備された東山古墳群が在って周辺の様子は僅か数年で見違えてしまいます。近付くとセンサーで感知され岩室内をライトアップして
見せてくれる古墳もあります。
![]() 東山古墳群から城山(貝野城)と妙見山
・展望619mピーク
東山古墳群から城山(貝野城)と妙見山
・展望619mピーク
平成16年5月妙見山
(693m旧・多可郡中町のシンボル)山麓の東山古墳公園内に「那珂ふれあい館」が完成し、東山古墳群をはじめ町内から発掘された出土品などが展示されています。野外には
播州歌舞伎などを演じられる舞台があり、山菜を採取したり・山に登ったりと大自然を感じる
活動拠点となっている。東隣には県内最大級の石室をもつ古墳など、
古墳時代後期の円墳16基を復元した東山古墳群公園があり、いにしえの文化を感じることができます。 ボランティアガイド、歴史資源を説明する案内板の設置なども行っています。
15号墳の玄室![]()
東は(ひむがし)と読み「日の向う風
(日向風=ひむかし)」という意味があって、古代人の崇拝する太陽を、毎朝真っ先に仰ぐ妙見山の麓にある東山こそ信仰と豊穣の地として、早くから開拓が進み鉄製農機具の普及と共に生産が増大する古墳時代後期
(4世紀)には、牧野・東山・安楽田等山麓に無数の墳墓が築かれていますが東山古墳群は横穴式石室を持つ7世紀・大化改新(645)頃に築かれたものとされています。
陶棺【12号墳出土品】
中町の妙見山麓一帯には4世紀頃~大化改新 (7世紀 645)頃に築かれた十群二百基以上もの古墳が確認されており、中でも妙見ゴルフ場や県立多可高校西隣に位置する
東山古墳群は兵庫県下でも最大の横穴式石室を持つ古墳や、巨石を用いた石室の古墳が多く、当時(6~7世紀)此の地方の豪族の力が窺え、東山1号墳は県下でも最大級(羨道~玄室まで約12.5m、
玄室部の長さ6.25m・高さ約3m)の規模です。また12号墳は天井石が落下したため石室の奥部が全く荒らされていない状態で残っており家型陶棺(長さ140cm・幅45cmで12本の脚と、
切妻風の屋根を模した蓋がある)が 原形をとどめた状態で出土しています。この陶棺は組合せ式の「須恵質切妻家形陶棺」と呼ばれるものですが、身や蓋に突帯がめぐり、全体にずんぐりとした形態を持っています。
陶棺は畿内の奈良・大阪・京都府等に分布しているが、兵庫県下では30例程を数える程度で全体の形が明らかになる例は極めて少なく、横穴式石室に安置された陶棺の出土自体稀だといわれるが丹波市でも発見例があり
(詳細不知!!?)播磨・山陰を結ぶ”氷上回廊”と呼ばれる加古川
沿いの
交通路と文化の関連付け等が推察され、きわめて異例であり貴重な資料となっています。当時の墓地は移り、今は妙見山麓・東山古墳群に隣接して研修センタ「多珂ふれあい館」が建設され、此の陶棺がセンター内に
展示され何時でも見学出来る様になっています。なを此の陶棺以外は石棺さえ一個も発見されていないといい、殆どが木棺で有ったと推察されます。ところが僅か100m程離れた民家の敷地内に在る「村東山古墳」から発掘された、
其の形態から組合せ式家型石棺は中町の中央公民館前に移設され現物保存されています。今回の古墳オフ(H17.01.23)に参加のメンバーには、中町ボランティア・ガイドの皆さんにお世話になった後の帰路に寄り、
西脇市大木町の鍛冶の神様・天目一神社にも立ち寄りました。
(現地 古墳案内板・パンフ・研修センタ内資料等を参照)
![]()
村東山古墳 多可郡那珂町中
研修センタ「多珂ふれあい館」の南西部にある鉄工所の資材置き場の様な地所有る村東山古墳に向かう。地区内の道からもポッカリ南に開いた玄室部が石垣上部に見えています。
石棺は中央公民館に移され、さらに近年直ぐ側の「那珂ふれあい館」芝生広場に開放展示されている。現場の石室は奥行き2m程しかない。石棺の出土した村東山古墳は石室を補強し永久に保存されている
…とあったが現場は昭和48年(1973)7月・造成工事中、敷地内の丘陵を切崩していて発見された様で、羨道部分等が壊されてしまった後石棺が出土した為・調査が行なわれたのでしょうか?。
![]() 村東山古墳
村東山古墳
残念ながら
玄室部だけしか残されていません。地主さんが埋葬者に祀っておられた花立だけが石垣上に残されていますが、其の地主さんも近年亡くなられたとか…玄室に入りたそうにしていた”海老珍さん”も2m程の垂直に近い石積を越えて近づくのは容易ではなさそうです。
出土した須恵器の年代や薄くて綱を掛ける突起のない形式等からも、古墳時代終期の7世紀末と推定されている横穴式円墳の規模は、
村東山古墳出土の組合せ家型石棺 H16.11.28
![]()
石室の幅約16m・高さ約1m・奥行き約27m?は墳丘全体の規模を推定してのものか!現地説明版は 雑木の中に倒れた枝まで有って読み取れない。 中央公民館に移設されている”組合せ式家型石棺”は底石・側石・蓋石
7枚で組み合わせられていて幅91cm・長さ208cm・高さ54cmあり、人骨の痕跡は認められなかったが内部の堆積した土砂の科学分析から、遺体が収められていたことが明らかとなっています。出土品には他に数個の須恵器
・土師器の破片と少量の鉄釘も出土しています。”組合せ式家型石棺”完全な形で出土状態が明らかなものは極めて少なく県指定(昭和52年(1977)重要文化財となっています。
(現地 村東山古墳/同・石棺展示説明板 多可郡教育委員会 参照)
![]()
道ノ上古墳 アカ山 147m 西脇市羽安町
羽安町から市原町のR427に合流する道筋に道ノ上古墳があります。南端を西脇市野中町の
天目一神社付近に伸ばす南端の大木城から・中央の点名:下曽我井(三等三角点 210m)を最高として
北端を杉原川に落とす南北2km程の 低丘陵北端部羽安町の通称アカ山と呼ばれる標高Ca147mの山頂部に築かれています。かつて眼下に望む杉原川に沿っては国鉄加古川本線の枝線
・鍛冶屋線が走っていて武嶋山を東に見て羽安町(廃線跡に散策道とモニュメントがあります)から、
ほぼ90度:西に流れを変える角にあって、
![]() 道ノ上古墳(稲荷社のある北端ピークから)
道ノ上古墳(稲荷社のある北端ピークから)
黒田庄町から石原阪を越えて中町に入り正面(北に石原北山山城や
森本城)と杉原川沿いの街道を見張るに適した位置で、北面は断崖状の要害であり砦跡かとも思い登ってみます。羽安町の県道236号線側から古墳までは案内標識が在るので道順説明は不要ですね。
南へ延びる鞍部に祠があり、山頂部は古墳と向かい合うように同じ墳丘状の平坦地には稲荷の小祠がある。道ノ上古墳遺構は側直径26.4m・高さ3.72mの当地域では大型の円墳といわれ、
乱掘の痕跡もなく遺存の状態も良好といわれます。
道ノ上古墳(西面・墳丘の葺石![]()
時代を決定する出土品がないが立地や外部施設、埋葬施設の推定から古墳時代前期~中期 (4~5世紀)頃に築かれた可能性を推定されています。円墳なら・大概は横穴式かと思われますが埋め戻されてか墳丘しかわからない。
墳丘の斜面に河原石による葺石が認められるほか、墳丘の裾には其れよりひとまわり大きな割り石による裾石が存在する。墳頂平坦面中央に南北方向の石材が存在することから、埋葬施設は竪穴式石室と推定されており兵庫県指定
【昭和55年(1980)3月25日】文化財です。
(現地・道ノ上古墳・県教育委員会の平成4年11月の案内板 参照)
![]()
滝ノ上古墳群と 岡ノ山古墳と「日本へそ公園」 西脇市上比延町244
R175号線の寺内北交差点で県道36号に入り加古川に架かる緯度橋を渡ります。川床には日本地図が描かれ・川向にはJR加古川線「日本へそ公園」駅があり、側には西脇市出身で得意なポスター画でも知られるアーティスト・横尾忠則氏の作品が
展示されている岡之山美術館が建っています。
![]() 日本のへそ公園:正面にテラドーム
日本のへそ公園:正面にテラドーム
小さな無人の駅舎に三両編成の列車が停車している構図が緯度橋の中程からは望めます。其の東側の森へ南北から階段の散策道を登ると「日本へそ公園」の駐車場に出て公園内の散策やテラドームに向います。
「日本のへそ公園」駅と岡之山美術館![]()
其の駐車場の間仕切り状態の林の中に円墳・方墳が 点在する滝ノ上古墳群があります。
公園の北を東西に走り抜ける県道の北側一帯も滝ノ上古墳群ですが
田畑が拡がり 其の向こうに民家が見え、更に北方の墓地へと平坦地が続くので発掘調査後に消滅したものか?。痕跡も有りませんが西端部の雑木林に何基か残っている気配ですが?。遺跡分布図等での確認は未。
![]() 経緯度交差点の標柱
経緯度交差点の標柱
この河川段丘の段丘崖の雑木林の西にある加古川河川敷き公園内へは、
緯度橋からも螺旋階段を下りると”東経135度線・北緯35度線が交差する標識「経緯度交差点標柱」が有って、日本列島の中央に位置することから西脇市が「日本のへそ」とよばれます。大正10年(1921)建設省国土地理院の前身である
陸軍参謀本部陸地測量部によって 計測されたもので、標柱の文字は終戦時の首相で、時の呉鎮守指令長官鈴木貫太郎海軍大将の書です。
滝ノ上古墳:県道側近くに在る方墳
![]()
東経135度は日本標準時を表わす子午線で日本の東西の中心であり、北緯35度も日本国土が25度から45度にわたるところ、
正に南北の中心でもあることから西脇市の此処を「日本のへそ」と愛称されています。古川を渡った県道36号(西脇篠山線)南側の「日本のへそ公園」と北側に数10基の古墳が分布しているとされ、以前から「へそ公園」内の滝ノ上古墳群や公園の東側に位置して盛り上がる比高約60m程の独立低丘陵の
岡之山山頂部に築かれた岡ノ山古墳がある。
![]() 滝ノ上古墳の円墳2基
滝ノ上古墳の円墳2基
岡之山の東側に存在する西岡古墳群にも寄ってみました。「日本のへそ公園」駅の東一帯に拡がる公園には
「地球と宇宙をテーマとした科学館」で地球・月・天地軸をイメージした外観は、
日本のへそ公園のシンボル的存在です。にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」では81cm大型反射望遠鏡があり、宇宙の神秘に触れられる天体観測会も開かれ、地球に関する資料等が展示されています。
滝ノ上古墳:小さな円墳だが周溝を残す![]()
星座や方位に関した遊具や
野外ステージも設けられています。其んな公園内の西端部、駐車場に並んで一部残された緑地部は、散策道として整備される事もなく自然林のままに放置されています。駐車場からも小さな墳丘の幾つかが見られます。
JR公園駅へ降る南端部にも墳頂部に凹みを見せているもの、円墳の外周郭の残存部を見せるものもあり、北方の円墳には周濠(濠よりは溝状が妥当かも!)らしい窪地に取巻かれているものもあります。
![]() 西岡古墳群:円墳?の外郭底部を残す古墳
西岡古墳群:円墳?の外郭底部を残す古墳
発掘調査後に消滅したという滝ノ上古墳群の第20号墳から出土した遺物類は西脇市指定(平成6年6月21日)文化財として”西脇市郷土資料館”に収められています。岡ノ山周辺には、
古墳時代前期(4世紀後半頃)から後期
(7世紀前?)にかけて多くの古墳が築造されていますが、殆どが径5~6m程度の小規模な古墳からなり、羨道を伴う横穴式石室はなさそうで、大部分は方墳や円墳の墳丘に竪穴式石室を置く構造の様です。
西岡古墳群:浅い周溝を残す帆立貝式古墳![]()
テラ・ドーム南側の公園に設けられた長い”ジャンボ滑り台”から山頂部を周回する散策路があり、
其の最高所付近に「兵庫県指 定文化財:岡ノ山古墳
昭和62年3月24日」の案内説明板が設置されています。此処から藪っぽい尾根沿いの踏み跡を辿ると岡ノ山古墳の後円部の墳頂に続いています。岡ノ山古墳は全長51.6m・後円部経35.5m・高さ7.7mで前方部幅12.9m・高さ3.7mを測り、
前方部は細長い柄鏡式で、
定文化財:岡ノ山古墳
昭和62年3月24日」の案内説明板が設置されています。此処から藪っぽい尾根沿いの踏み跡を辿ると岡ノ山古墳の後円部の墳頂に続いています。岡ノ山古墳は全長51.6m・後円部経35.5m・高さ7.7mで前方部幅12.9m・高さ3.7mを測り、
前方部は細長い柄鏡式で、
![]() 岡ノ山古墳:後円部から前方部を…!!藪!!
岡ノ山古墳:後円部から前方部を…!!藪!!
後円部は2段築成されている。外部施設は石垣状の葺石が認められるが埴輪類は確認されていません。埋葬施設は墳丘主軸に平行した竪穴式石室と推定
されています。
確実な築造年代は出土遺物が知られていないため不明ですが、前方部が柄鏡式であること・山頂に築かれていることから、古墳時代前期でも早い段階(4世紀前半)の築造である可能性が高いものと推定されています。
滝ノ上古墳は駐車場の前![]()
墳丘の依存状態はきわめて良好・・・!!)というのですが、背を屈めて雑木藪の尾根筋を進んで
墳頂の後円部に至るものの、以前訪れた時同様に古墳の全体像も部分の状態も見えず素人の悲しさ!、確認する術を知らず・何も判らず引き返したが、西脇市・多可郡内唯一の前方後円墳で、古墳時代前期のもの。
(現地:岡ノ山古墳 平成7年2月の案内板 他:平成4年11月の案内板 県教育委員会 「日本のへそ公園」パンフを参照)![]()
寺内古墳群 西脇市寺内
 丹波市からR175号線を南下
「道の駅 北はりまエコミュージアム 」の案内標識を見て右折。NPO法人による「地域づくり活動拠点の北播磨田園空間博物館」は地元北播磨(西脇市・多可町<旧多可郡各町>の自然:歴史:文化:産業から住民生活そのものまでも含めた
有形・無形の地域資源のサテライト。西脇市街地への往復時には四季折々のイベント等の新情報収集に立ち寄り利用します。
丹波市からR175号線を南下
「道の駅 北はりまエコミュージアム 」の案内標識を見て右折。NPO法人による「地域づくり活動拠点の北播磨田園空間博物館」は地元北播磨(西脇市・多可町<旧多可郡各町>の自然:歴史:文化:産業から住民生活そのものまでも含めた
有形・無形の地域資源のサテライト。西脇市街地への往復時には四季折々のイベント等の新情報収集に立ち寄り利用します。
![]() 寺内古墳群:7号墳の玄室(奥壁)
寺内古墳群:7号墳の玄室(奥壁)
此の「道の駅 北はりまエコミュージアム」からは西側の交差点を左折して・あじさい寺の西林寺へも程近い。西方の山に向って直進する広い舗装道路は
西脇多可広域斎場「やすらぎ苑」に入ります。其の敷地内の入口には・広い施設と駐車場等に丸く囲われた芝生が拡がり、お椀を伏せた様に数多くのドーム状に、盛り 上がりを見せる円墳が姿をみせています。此の「やすらぎ苑」敷地内の芝生広場が 史跡公園として整備された寺内古墳群です。専門的な研修や解説資料は、
西脇市郷土資料館に出土品展示や、西脇市教育委員会の【寺内古墳群西脇市文化財調査報告書第13集】等があるので参照してください。
上がりを見せる円墳が姿をみせています。此の「やすらぎ苑」敷地内の芝生広場が 史跡公園として整備された寺内古墳群です。専門的な研修や解説資料は、
西脇市郷土資料館に出土品展示や、西脇市教育委員会の【寺内古墳群西脇市文化財調査報告書第13集】等があるので参照してください。
寺内古墳群:7号墳の玄室(底部の配水溝)
![]()
古くから「十三塚」と呼ばれて 存在が知られていた群集墳は、分布調査によって古墳28基が確認されています。
径5m~7m程度の小円墳が密集して築かれているなかで寺内7号墳だけは・此れ等群集墳の北端に在って特別に目立つ大きな円墳で、 埋葬部は全長8.5m・幅1.7m・天井の高さ 2.2mの無袖式・横穴式石室は、ほぼ南方に半壊した羨道部を見せて開口しています。
墳丘は地山を削り出して、一辺18m正方形の基 壇を造り、
其の上に18m×12mの長方形に土を盛り上げて築かれた方墳です。天井石は入口側が失われていますが、残っているものは長さ3m・幅1.5m以上の巨大なものです。 床には石組による幅20cmの暗渠排水溝が設けられ其の上面に石を敷いています。
壇を造り、
其の上に18m×12mの長方形に土を盛り上げて築かれた方墳です。天井石は入口側が失われていますが、残っているものは長さ3m・幅1.5m以上の巨大なものです。 床には石組による幅20cmの暗渠排水溝が設けられ其の上面に石を敷いています。
![]() 寺内古墳群:群集墳の状況
寺内古墳群:群集墳の状況
埋葬時に納められた副葬品は石室が古くから開口していた為、荒らされていたが須恵器や土師器の土器・鉄製の馬具・滑石
【かっせき:鉱物の中で最もやわらかいもののひとつで利尿作用・消炎作用があるとされ、漢方薬として配合されるので、後述の呪術祭祀としては:このうえない用具と考えられますが…】
製の臼玉や子持勾玉等が出土しています。此のうち特異な形態をもつ・子持勾玉は加古川流域では2例しか報告されていないという。 集落遺跡から出土する事が多く、大型の勾玉の表面に勾玉状の小さな突起(簡略化した小型の勾玉)を両脇や背中
・腹に付けられていることからも、子孫繁栄や 農作物の豊穣等
・自然の恵みを祈願したものか?副葬品とは別に・呪術的な祭祀の道具として使用されたものとも考えられている様ですが、 他にも色々な説が解かれているようです。古墳時代中期(5世紀頃)に出現し7世紀頃まで作られています。
農作物の豊穣等
・自然の恵みを祈願したものか?副葬品とは別に・呪術的な祭祀の道具として使用されたものとも考えられている様ですが、 他にも色々な説が解かれているようです。古墳時代中期(5世紀頃)に出現し7世紀頃まで作られています。
寺内古墳群7号墳:配水溝が羨道部から玄室内へ続く![]()
寺内古墳7号墳の床面には排水溝が設けられており、
其の上に石が敷き詰められた丁寧な造りになっています。出土した副葬品等の特徴からも 古墳時代後期の七世紀中頃(630~660年:大化年間頃か)築造と推定されます。また此の頃の飛鳥地域の古墳には方形や多角形のものが多く
寺内古墳7号墳も此れに影響され・真似て築かれた可能性は多分に考えられます。大和・飛鳥地域の有力者との関係を築いていた此の地域の首長級墓として7号墳が築かれた事で、其れをきっかけとして他の27基!!の小古墳が次々と
造営されていった様です。寺内古墳群はその数少ない群集墳で、群集墳の構造やひいては社会構造を知るうえで貴重な遺跡であるため現地に保存されています。
(現地:寺内7号墳の案内板 等参照・索引)
![]()
八日山古墳1号墳
西脇市下戸田字八幡ノ下
R175号線を南下して上戸田交差点を過ぎると右手に迫る丘陵部の南山裾部には、新館増設中の「市立西脇病院」が見えてくる。丘陵部の頂が八日山(2109m)の独立丘陵で南山麓には
下戸田八幡神社が鎮座し、市 立西脇病院前から
石鳥居を潜って参道が延びています。参道は車道を挟んで続きますが、その車道を東へ・または神社境内と社務所裏手の広い山道を約60mほど進むと応供寺跡に出ます。応供寺跡には阿弥陀堂と石垣檀と、
立西脇病院前から
石鳥居を潜って参道が延びています。参道は車道を挟んで続きますが、その車道を東へ・または神社境内と社務所裏手の広い山道を約60mほど進むと応供寺跡に出ます。応供寺跡には阿弥陀堂と石垣檀と、
![]() 下戸田八幡神社と八日山古運1号墳(右手石段上)
下戸田八幡神社と八日山古運1号墳(右手石段上)
檀上には四箇所の柱の礎石が残る鐘撞き堂があり室町時代の
「応供寺十二天の掛け軸」が郷土資料館(童子山公園・図書館隣上)に展示保管されているという。阿弥陀堂傍からは案内導標が完備した八日山への周回登山コースが延びていて、八幡神社背後を取巻く尾根沿いに神社南西部
:上野の池端にある登山口へと約1時間 もあれば散策できそうです。
下戸田の八幡神社では「笑え 笑え・ワッハッハ・・・」と黒い八角棒や白扇を持ち、上下させながら大声で笑って拝殿をまわり、神相撲では頭人が東西に分かれて手のひらを合わせて引き押しの相撲が行われ(勝敗は既に決められている!!)て豊作を祈願する・・・
もあれば散策できそうです。
下戸田の八幡神社では「笑え 笑え・ワッハッハ・・・」と黒い八角棒や白扇を持ち、上下させながら大声で笑って拝殿をまわり、神相撲では頭人が東西に分かれて手のひらを合わせて引き押しの相撲が行われ(勝敗は既に決められている!!)て豊作を祈願する・・・
応供寺跡の鐘撞き堂跡と阿弥陀堂![]()
”西脇市指定民俗無形文化財の「お笑い神事」で知られます。神社境内広場の中央に鉄骨の舞台が残されています。
昇降階段部は鍵付きで 閉鎖されているので常設ステージのようですが、仮設ではなく舞殿か、舞楽の舞台であれば境内に違和感無く溶け込むものと思えるのですが!!?。仲哀天皇が亡くなられた後、神功皇后は身籠ったまま武内宿禰とともに
「三韓征伐」朝鮮半島に出兵します。朝鮮からの帰途に福岡県宇美の地(現在の 宇美八幡)で応神天皇を出産されます。八幡神社のご祭神の応神天皇が幼少のころ、大臣:武内宿禰(すくね)や付き人が相撲をとってあやしている様子は、
ユニークな神事として「お笑い神事」動画で紹介され宮司より其の由来が語られています。
宇美八幡)で応神天皇を出産されます。八幡神社のご祭神の応神天皇が幼少のころ、大臣:武内宿禰(すくね)や付き人が相撲をとってあやしている様子は、
ユニークな神事として「お笑い神事」動画で紹介され宮司より其の由来が語られています。
![]() 下戸田八幡神社と
八日山古運1号墳(右手石段上)
下戸田八幡神社と
八日山古運1号墳(右手石段上)
拝殿前に立つ狛犬像は江戸時代末期の嘉永3年 (1850)加東新甼(現:加東市新町か?)の石工:西山喜助の銘があった。 昭和31年(1956)7月、神社境
 内拡張工事の際に発見された八日山古墳1号墳が在る。
本殿と並び其の東側丘陵斜面、石段上には玉垣を廻らせた平坦地の中央部に埋葬施設の主体部が有り、板石で囲い・覆われた長さ186cm・幅45cm・高さ30cmの箱式石棺だけが安置されています。
内拡張工事の際に発見された八日山古墳1号墳が在る。
本殿と並び其の東側丘陵斜面、石段上には玉垣を廻らせた平坦地の中央部に埋葬施設の主体部が有り、板石で囲い・覆われた長さ186cm・幅45cm・高さ30cmの箱式石棺だけが安置されています。
応供寺跡の鐘撞き堂跡と阿弥陀堂![]()
玉垣囲いの状況からは当然墳丘部分が不明ですが、発見が拡張工事の際だといい・字名の「八幡ノ下」から考えても、
現状残されている箱式石棺は参道途中の車道から本殿前への参道付近で発見された、直径5m程の円墳の表土下55cmの所に主体の石室が有ったという。古墳時代後期:七世紀後半(700頃)の築造と推定されます。円墳からは石棺だけを、
本殿東隣へ移設復元保管されているものかと思えます。八日山古墳は遺跡分布図によると1~6号墳が在り何れも高さ1m未満、東八日山古墳が1~3号墳があり消滅したが下戸田古墳2~4号墳が記載されています。
(道の駅に有った「西脇まちんなか歩こうMAP」八幡神社宮司による案内板 を参照)
![]()
上本町大塚古墳1号墳 西脇市上本町字大塚
童子山公園の展望台から続く散歩道を東側の「椿坂」に下る。宅地の横のコンクリート石段道を、椿坂に降り
て来てまだ歩いていなかった山側へ、
ほんの数m?進むと上本町公民館分室前の分岐、此処を東側に向かうと細くて急斜な、幅1.5m程のコンクリート山道が丘陵に続く。丘陵入口の最奥の民家裏手に妙見堂が建ち、境内の丘陵側は竹藪が続き其の境はフエンスが取り囲んでいます。
![]() 妙見堂裏手に有った「大塚古墳」案内板
妙見堂裏手に有った「大塚古墳」案内板
妙見堂裏手の西端と山道との間
・1m程の段差で竹藪となるフエンスの傍に「大塚古墳…5世紀 直径30m 高さ3m」の古い案内板が立つている。案内板の先の高みに説明にあるような、大きな古墳の盛り上がりは見られない。高さ1m程の土砂の高まりの此処が
大塚古 墳で、発掘調査後現状に埋め戻されず
放置された状態なのかは不明?。藪と枯れ竹で荒れ放題の竹林の中は平坦な段差が彼方此方にあるが、部分には古墳跡と思えるような箇所もある。その緩やかな傾斜面の奥の最高所部分に円形の高みが見える。直径30m程、高さも3m程。
墳で、発掘調査後現状に埋め戻されず
放置された状態なのかは不明?。藪と枯れ竹で荒れ放題の竹林の中は平坦な段差が彼方此方にあるが、部分には古墳跡と思えるような箇所もある。その緩やかな傾斜面の奥の最高所部分に円形の高みが見える。直径30m程、高さも3m程。
大塚古墳:周囲にも古墳が点在か…?![]()
其処に”個人私有地につき立ち入り禁止…・”の貼り紙が!!?。
既に遅し…だが用を成さない貼り紙ではある。 申し訳なく…気拙い思いで引上げるが、石室等の石材も残さない墳丘部だけの古墳では専門知識の持ち合わせがないと、古城砦の小さな自然地形を利用しただけの曲輪を見ている様で味気ない…!!県の埋蔵文化財保護の手引き
・行政地区マップ (遺跡分布図)に上本町大塚1号墳(円墳・直径20m・高さ3m・葺き石が残っている様!!?)とあるのが此れの様で近くに2号墳も在るようです。
![]()
西岡古墳群 西脇市上比延町
「日本のへそ公園」を出て県道36号
(西脇篠山線)を東に向かい、最初の信号を右折して50m程進むと岡之山東山麓と車道を挟んで東側 ・民家の南側植林の中には数基の墳墓の隆起を見ます。円墳7基程と帆立貝式古墳1期で構成された古墳群で、
互いに近接して群集しているが保存状態は比較的良い。
![]() 西岡古墳群:円墳の水を湛えて残る周濠
西岡古墳群:円墳の水を湛えて残る周濠
林の中に残る円墳等には周溝の形状が判る程度に残っており、
一基は水を湛えて良好な周濠の姿を見せています。古墳が点在する一帯の植林は岡之山東裾(西面)と南面には
良好な状態で残る西岡古墳群![]()
地区内の車道が東西・南北に走り、県道294号に接続し、北側から東側を民家と田畑が囲み、此の狭い一角が幸いにも植林として残っている事、民家の庭にさえ隣接していながら宅地や畑地として造成破壊されずに残り、良好な状態で残されている事を感謝です。
都会では有り得ない奇蹟ですね・・・(^_-)-☆
![]()
小苗古墳群
西脇市黒田庄町
 R175の旧佐治川 (加古川)を南に渡ると、丹波市でも早い時期に造られた道の駅:山南町の簡易パーキング「さんなん仁王」、
東方からの篠山川が此処で合流し加古川と名を変えて流れ出る。合併で氷上郡が丹波市と名称変更なったと同様に佐治川流域の歴史が加古川に吸収されてしまうと、
R175の旧佐治川 (加古川)を南に渡ると、丹波市でも早い時期に造られた道の駅:山南町の簡易パーキング「さんなん仁王」、
東方からの篠山川が此処で合流し加古川と名を変えて流れ出る。合併で氷上郡が丹波市と名称変更なったと同様に佐治川流域の歴史が加古川に吸収されてしまうと、
![]() 墳丘部の斜面を埋めるのは「葺き石」?
墳丘部の斜面を埋めるのは「葺き石」?
古代~中世の歴史的体系には一々補足説明が必要になるよう要素が出てきます。佐治川が加古川に名称統合して県下一の長河になっても、
行政管理?以外どんな重要な意義・意味があるのかはわか らないが…
丹波:佐治川 (現加古川)と播磨:加古川では地系・風土・気候等々も異なり、未だに此れらに関わる場合は加古川として、画一化して説明出来ず丹波側では「旧佐治川」と補足しています。
らないが…
丹波:佐治川 (現加古川)と播磨:加古川では地系・風土・気候等々も異なり、未だに此れらに関わる場合は加古川として、画一化して説明出来ず丹波側では「旧佐治川」と補足しています。
同古墳群では最大規模?の石室内部
![]()
そんな要らぬ苦悶から解放され西脇市の境界・黒田庄町(此処も旧多可郡で西脇市に編入・同:多可郡の中町・加美町は那珂郡に!!)に入る。加古川の東岸沿いにJR加古川線が走り
妙見山~白山の主尾根から延び出す西への枝尾根が落ち込む末端部裾の緩斜面に小苗古墳群があります。尾根筋から小苗古墳群に下る鞍部付近にも
 古墳のものと思える石材が有るのですが不詳?。
小苗集落へは県道294号沿い JR加古川線船町駅側を北方に約500m程・標識が出ています。西方に見える至り山の麓が篠山川・旧佐治川(現:加古川)の合流地点です。
古墳のものと思える石材が有るのですが不詳?。
小苗集落へは県道294号沿い JR加古川線船町駅側を北方に約500m程・標識が出ています。西方に見える至り山の麓が篠山川・旧佐治川(現:加古川)の合流地点です。
![]() 埋葬施設の石室部を残す古墳
埋葬施設の石室部を残す古墳
民家の間を東側へ直角に曲がる狭い車道を、踏切を渡り山に向って直進・鹿猪避けフエンスを開閉して進むと 墓地前に駐車スペース。
此処から恐ろしく急斜面を直進する簡易舗装道が、弥勒菩薩を祀る祠に向っています。この右手斜面一帯に10数基ばかり、高さ1m弱・長さ4m前後・幅1m程の小円墳が点在しています。墳丘と石室を残すものは3基程、他には石室の基部や石材が残り
・また崩壊・陥没しているものが山林内の 比較的狭い範囲に
密集している様です。 小谷を挟んだ向かいの斜面や、祠上部にも点在しているのかもしれませんがJR本黒田駅西方の病院に寄ったついでの寄り道・古墳詳細及び遺跡分布図等を調べていないので古墳の特徴や号数等は不明です。
比較的狭い範囲に
密集している様です。 小谷を挟んだ向かいの斜面や、祠上部にも点在しているのかもしれませんがJR本黒田駅西方の病院に寄ったついでの寄り道・古墳詳細及び遺跡分布図等を調べていないので古墳の特徴や号数等は不明です。
古墳の石室内部![]()
小苗古墳群では最大規模か?比較的大きな古墳には並べられた石垣状の葺石が残っている様です?。
石室が開口する羨道部片側基部が残り、周囲の石室部4~5m程度に比べても長さ7m程は群中の首長格クラスのもの?、また周囲に集積する残石・石塁!!?が方形に延び出している様に見え、法螺貝式の様に思える。たしか全:横穴式石室を持つ円墳?とされている筈。
一部に半端でない小石が集積しているのは、後世の人為的なものか?専門的な報告書等を調べないと素人には無理.ですね…(^^ゞ
![]()
経ヶ芝古墳 西脇市平野町字経ヶ芝
西脇市板波町の
鳴尾山城西山麓に職業訓練センターがある。直進して未舗装の広い駐車場奥のテニスコートから経ヶ芝古墳(復元)公園までの30m程山道を登ります。右手に直進の山道は高圧線鉄塔への巡視路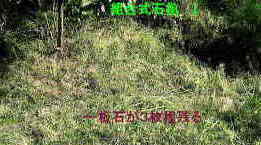 ですが、以前此の道を利用して鳴尾山城へ登った事があります。経ヶ芝古墳も元は此処より200m程南の尾根上に在ったものを、
発掘調査後・現在地に移築して復元されています。墳丘斜面には裾から1m程に石を敷きつめて葺かれ、
ですが、以前此の道を利用して鳴尾山城へ登った事があります。経ヶ芝古墳も元は此処より200m程南の尾根上に在ったものを、
発掘調査後・現在地に移築して復元されています。墳丘斜面には裾から1m程に石を敷きつめて葺かれ、
![]() 雑草に覆われた墳丘部:4年前は石室・石列等が良く観察出来たのに(^^ゞ
雑草に覆われた墳丘部:4年前は石室・石列等が良く観察出来たのに(^^ゞ
基底部に列石が巡る1辺約11mの方墳です。葺石加工し易い為か?コーナーR(四隅に丸み)を持たせています。墳丘の主体部には板石を組合せた箱式石棺が2基東西に並んでおり、
石棺内部には朱が塗られていましたが、副葬品が全くないため築造時期は不明で前期と推測されています。鳴尾山に寄ってから 城址へ降りるつもりなので西側の職業訓練所の奥の駐車場へ車を入れてスタートします(AM6:45)。最奥 にテニスコートがあり此処から山へ向かい 古墳までの散策道があります。火の用心「北攝長田野線No.8」標識のある巡視路から
山道になりますが左手直ぐのところに、小公園化された経ヶ芝古墳(復元遺跡)があるので立ち寄ります。
にテニスコートがあり此処から山へ向かい 古墳までの散策道があります。火の用心「北攝長田野線No.8」標識のある巡視路から
山道になりますが左手直ぐのところに、小公園化された経ヶ芝古墳(復元遺跡)があるので立ち寄ります。
経ヶ芝古墳:石が敷き詰められた墳丘斜面!
![]()
西脇市教育委員会の立派な説明案内板が立つが、説明文字や図が白っぽく薄れて読めなくなっているのは残念です。それ以上に残念なのは平坦だった墳丘上の主体部は荒れ、
雑木・雑草に覆われて殆ど判別出来ない。小さな組立式石棺さえ咄嗟には判らず4年前・此処から鳴尾山に登る際に寄った時と比べれば現状が嘘の様です。
(現地 経ヶ芝古墳案内板 参照)
![]()
下山古墳 西脇市冨吉南町249
R175号線の黒田庄町津万井を右折しR427号線で市原町方面に向う峠越えの道・西脇健康ランド(ホテル)の手前の冨吉南町交差点から富田町へR427号の東を平行に走る道は、 そのまま林道を西林寺(アジサイ寺で知られ
島村城が在り、途中の峠からは坂本城への最短距離なので利用した事がある)へ抜けられます。
此の車道の冨吉南町と富田町の中程が日野で東側に緩やか延びていく日野団地内を抜ける車道の先にフェンスに囲まれ内部を見られない古墳があることは知っていたが…。
![]() 下山古墳玄門部:両袖式と”持送り”が判る
下山古墳玄門部:両袖式と”持送り”が判る
この古墳時代後期(6世紀後半)築造の古墳が西脇市指定文化財(昭和57年3月30日)で有ること、封土がスッカリ失われて横穴式石室が露出し、篠山の”石くど”や明日香の”石舞台”状態になっていること、フエンスに囲まれ中に入れないばかりか写真も思うように撮れない状態ですが、其れでも西脇市内最大規模の
巨石墳で大きく開いた高く広い石室内部まで、肉眼で観察出来て鳴尾山城と 経ヶ芝古墳の寄った帰路に立寄って良かった。今日の西脇市の古横巡りで横穴式石室を見る事も無かったので、スケールの大きな巨石墳が見られただけで満足です。
下山古墳:全景(東方から)
![]()
直径20mの円墳と推定されおり、石室を南に開口した横穴式石室は全長7.4m ・玄室長4m・幅2.3m・高さ3.1m・羨道長3.4m・幅1.6m・高さ2.3mの両袖式です。
玄室内の画像はないが床面2.5m付近からは石材を内側に迫り出させて重量を分散させる”持送り”が見られます。フエンス沿いに玄室側に廻ると大きな岩の境目からも内部が見え、羨道と玄室部境の両袖式・持送りの状態を観察出来、
当地方の豪族の家族墓と推定されています。
(現地 下山古墳案内板 参照)
![]()
きつね塚古墳(明楽寺1号墳) 西脇市明楽寺町
西脇市から県道34号線を走り加西市に向かう県道24号線明楽寺交差点手前に「兵庫県重要有形文化財
貴都根塚古墳 宗教法人:神道大和教 輝根塚教苑 是より北100m」の看板を見る。南に岩混じりの荒涼とした丘陵が姿を露にしているが最高所には
水尾城がありました。ゴルフ場開発整備で発掘調査後・どうなったのか。 打ちっ放しで飛んだボールを拾うにも城跡へは岩登りに近い激登・・・お陰で城域保存には効果がありそうです。 県道34号を挟んで北側・県道24号との間、西方から延びだした段丘の先端部に輝根塚教苑が建ち、石段を上り切った苑内に稲荷社と拝殿?が建てられている。其の拝殿中央の正面が、きつね塚古墳の開口部に正対しています。 つまりは古墳自身が主祭神となっている為、墳丘や石室の上部は改変が著しい。顕彰碑には神霊が鎮まるとされる此の古墳には、再三の神の啓示があって、其の神意に基づ
いて礼拝堂が建てられた旨が刻まれていた。キツネ塚古墳 (全長7.9mの片袖式の横穴式石室をもつ)は古墳時代後期(7世紀後半)の築造で小豪族の墓といわれます。
なかには6石から成る組合せ式の家型石棺(長さ1.67m・高さ幅共に0.81m)があり、石棺の蓋石は頂上の平坦面の幅が広く、縄掛け突起も無いため家型石棺の最終段階に属するものと推察されます。県指定文化財【昭和55年
(1980)3月25日】となっています。地元住民によって発掘されたときには、棺内には2体の人骨と副葬品が発見されています。開口部には格子垣がはめ込まれ、正面は祭壇となり太鼓・榊・神棚等が置かれて近寄り難く、
側に寄れても石室内に安置されている石棺が確認できるのかどうかは疑問で、拝殿内の柱に懸けられた「重要文化財」の表板が空々しく見える。
(現地 きつね塚古墳 県教育委員会 平成5年11月案内板 参照)
本誌![]() 別冊
別冊![]()
