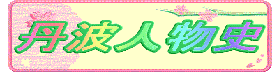
![]() (男性編)
(男性編)
1.山椒太夫 2. 3. 4.
山椒太夫 平安時代 年(1 )~ 年( ) 丹後七姫伝説の安寿と厨子王
森鴎外の小説『山椒太夫』で知られた
「安寿と厨子王」の物語の原作は、中世の説経節「さんせう太夫」だと言われており、諸処・各地に残る・その時代の庶民の口承文芸として形成されたもので歌舞伎・浄瑠璃をはじめ佐渡の文弥人形等芸能や浮世絵、
読本などの題材として様々な形で受け継がれ、物語の内容も同じではなく、時代とともに変化しているようです。中世末から近世にかけて、庶民の間に流行した語り物芸能【説教節や浄瑠璃等
】口承文芸の一つ「さんせう太夫」です。簓(ささら)説教」も呼ばれ、縁日等に社寺境内や辻堂にむしろを敷き、大きな傘を立てた下で、竹で作られた簓(ささら)という楽器を奏でながら、参詣人や通行人相手に
「算所・産所・散所(さんじょ)」に住む遊芸の徒(散所の徒:賎民芸能者!!)・説教師によって語られ民衆の涙を誘い、浄瑠璃・歌舞伎等の題材に取り上げられ親しまれた大道芸能で、
「山椒太夫」とは此の物語を語り歩いた芸人を指すものが、いつしか主人公の名と語り手の名が混同されたものとも考えられる様です。
村上天皇の天暦年間(947-57)奥川大守岩城判官将(正)氏が、
平将門の乱に荷担したとの冤罪によって【朝廷にお家再興を願い出る為京に向ったとか、朝廷の意に反して困窮する農民を救おうとし、筑紫国(大宰府)へ左遷されられたまま
消息の分からなくなった・・・とも】太宰府へ配流された父:岩城判官を尋ねて母と奥州を立った安寿と厨子王の姉弟は途中、越後の直井の浦(直江津)で姦賊・山岡太夫に捕えられ、母は佐渡へ
・安寿と厨子王は丹後由良の長者山椒大夫(三庄太夫:三つの荘園を持つ領主の意か!!)のもとへ売られてしまう。後はご存知・・・・虐使に耐えられず逃れ後に山荘太夫を誅した伝説の舞台となる東北(いわき市)・越後
(直江津市)から畿内・丹後の宮津市と移動・展開する物語には、其々; 具体的な土地
・ゆかりの場所が示されており、銅像や供養塔が建つ。小説や説教節とは別に:人物名やストーリーの展開にも違った内容の物語があり、似通った伝承が其々に残されているもので、
いわきの民話に後日談も有り安寿と厨子王が帰郷し、安寿が津軽の大領主、厨子王が小栗山の小領主となり不仲になる過程を記した「津軽の神いくさ」の話もある。
具体的な土地
・ゆかりの場所が示されており、銅像や供養塔が建つ。小説や説教節とは別に:人物名やストーリーの展開にも違った内容の物語があり、似通った伝承が其々に残されているもので、
いわきの民話に後日談も有り安寿と厨子王が帰郷し、安寿が津軽の大領主、厨子王が小栗山の小領主となり不仲になる過程を記した「津軽の神いくさ」の話もある。![]() 安寿姫塚にある歌舞伎絵の絵馬(舞鶴市下東)
安寿姫塚にある歌舞伎絵の絵馬(舞鶴市下東)
由良川河口には塩汲み浜・太夫屋敷跡や竹鋸でその首を挽かれたという首挽き松を残し、由良川を遡る舞鶴市下東に安寿姫を祀った供養塔
【安寿姫塚】もあります。山椒太夫の素性を語る口碑 ・伝承は少ないが算所・産所等の地名考からか?主に丹波国氷上郡(現:丹波市)の人との伝承もあります。丹波史年表に朱雀天皇の天慶8年
(945)久下村の山椒太夫が丹後由良に移るとある!?。丹波市山南町池谷は朝倉山椒の特産地で、久下(山椒)五郎兵衛(池谷久下氏の祖)は京都御所の山椒御用を承り、亀岡付近に山椒畑を所有して領主に献上・領主より江戸へも献上されています。
丹波市氷上町石生は石負(イソウ)長者の名の所縁か?・・・山椒を売って業とし、後に丹後由良に移り千軒長者と呼ばれたとの伝承もある。元来丹後わたりの散所太夫で由良長者と石負(いそう)長者
<千軒長者とも呼ばれた・・!!>の二つの顔を持つ人買いで、奴隷売買、人足(労働者)売買を業とした者。石負(石生)は由良川と加古川の分水界「
水別れ」にある地で、二つの川の因縁が絡んでいると言い伝えられた所。山椒太夫はその因縁の上にドッカと大きな屋敷を構えたと散所の伝説にある。
安寿と厨子王の逃避は舞鶴
:安寿姫塚の項に記すべき内容ですが、序に此処に紹介。
●在る日・姉は母から託された守り本尊の地蔵尊像を、弟に渡して躊躇う弟を屋敷から遁がし、姉は入水自殺を遂げます
(説教節では凄惨な火責め・水攻めの拷問によって殺されます。其の前:山椒太夫の屋敷で姉弟が逃亡する話を聞いた太夫の息子・三郎が、二人の額に焼印を押される火傷を負ったとき、 此の地蔵尊像に祈りを捧げると疲みや傷が消えたという)。
一方・厨子王は中山国分寺に遁れ、僧:曇猛律師の庇護により都に無事辿り着き、守り本尊の地蔵尊像の御縁により関白師実に見出され養子に入いる。厨子王が岩城判官:正氏の子であることが判り・元服して父の跡を嗣ぎ正道を名乗ります。
天皇から丹後の国司に任ぜられます【但馬も丹後も丹波だったが第43代元明天皇の和銅6年(713)に丹後国が設けられます】其れを機に人身売買を禁じ、母の行方を追って佐渡に渡り、この地で盲目となった母と出会う。
「安寿恋しや ほうやれほ 厨子王恋しや ほうやれほ・・・」涙のクライマックスと、山椒大夫が奴隷として使っていた人々を解放する「山椒大夫」の物語終焉も、厨子王が安寿の菩提を弔うために建立した丹後国の銕焼地蔵の御堂建立の由来を語る、
仏教説話の善悪因果応報・仏の功徳加護を強調して説く説経節「さんせう太夫」では、庶民の願望を物語に映して、厨子王(正道)に捕らえれた山椒大夫は、首だけ地から出して生埋めて、民衆が見守る中・竹の鋸で、其の息子・三郎に
挽かせるという復讐の刑罰を与えます。
宮津市由良の如意寺は、山椒大夫の首塚や安寿・厨子王姉弟の額の焼印を、身代わりとなって白毫に傷を負った地蔵菩薩が「銕(金)焼地蔵<京都府指定文化財>」として祀られています。
如意寺には「山庄畧(さんしょうりゃく)由来 (江戸時代後期)」の版木が残され、丹後由良に住み・地頭:大江時廉(ときかど)から国分寺の普請を任され、其の手柄により由良庄・河守庄・岡田庄の三つの庄の代官となり 勢力を振るった
「三庄太夫」とも云われます。此処での岩城判官政氏は大江時廉の讒言(ざんげん)によって自害し、母・姉弟は旅に出て山岡太夫に騙され売られる・・・筋書き。
なを:鵺(ぬえ)退治で有名な摂津源氏の末裔・源頼政は、
この対志王丸(厨子王丸)がモデルと言われ,兵庫・西脇市の金城山登山口の長明寺には源頼政
・鵺退治の像と源頼政の墓があります。
(丹波人物誌 久下村誌 丹波史年表 舞鶴市:安寿姫塚の由来 ウィキペディア等を参照)
![]()
年( )~ 年( )
![]()
年) ~ 年() ![]()
